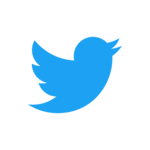三田尻御茶屋-英雲荘と大観楼-
萩往還の終点にある三田尻の御茶屋は、藩主の参勤交代や来客迎賓等藩の公館の役割を果たし明治以降は毛利家の別邸として使用された。昭和14年に防府市に寄贈され、防府に縁の深い毛利重就(英雲公)の法名から「英雲荘」と命名される。
*毛利重就 藩の財政を立直した名君で防府には、大規模な塩田を築いた。また、藩主隠居後に側室や子女とともに三田尻御茶屋に居住した。
文久3年、政変で京を追われた三条実美ら七卿が約2ヶ月間、英雲荘の2階にある大観楼に滞在(写真参照:英雲荘と大観楼・七卿の間)し、藩主父子や高杉晋作らが訪れ、国事を語り合った。
また、御茶屋の敷地内に置かれた招賢閣には、京での尊攘派の失脚に伴い脱藩して集まった浪士たちが寄宿して修練しながら、奇兵隊とともに七卿の護衛に当たった。(特殊任務にも就き、諜報活動や池田屋事件、禁門の変などにも参加)
浪士の中には、久留米の真木和泉、肥後の宮部鼎蔵、土佐の中岡慎太郎、福岡の中村円太などもいた。
当時は、御茶屋の近くまで港があり、軍港としての役割も重要で禁門の変、戊辰戦争の際もここから出港している。
また、高杉晋作が下関で挙兵した後、20名の決死隊で海軍局を襲撃し、軍艦を奪取したのもここである。
現在は、埋立でほとんどが消失しているが、外周水路の遺構(写真参照:三田尻御船倉跡)に面影を見ることができる。
(記述:吉本良太郎)